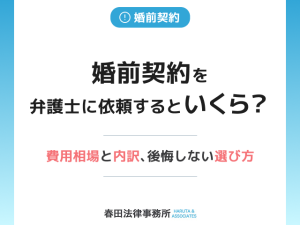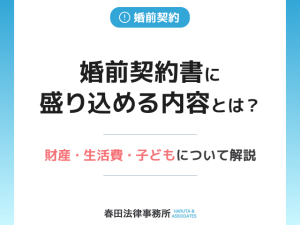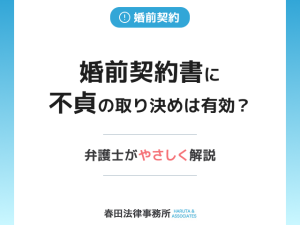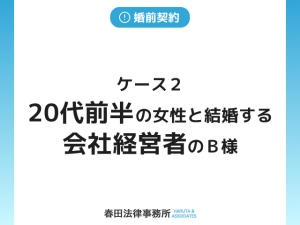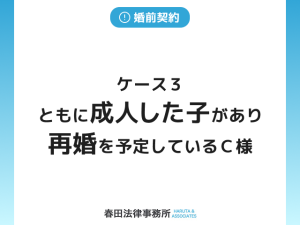婚前契約における婚姻費用、養育費の定め方
最終更新日: 2025年07月17日
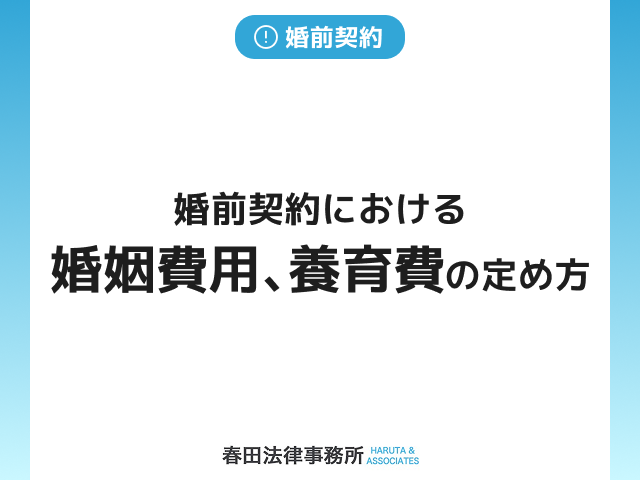
夫婦関係が良好な状態では、婚姻費用(生活費)について揉めることは多くはありませんが、夫婦の信頼関係が崩れ、別居や離婚協議に至った状態では、婚姻費用、養育費の金額は非常に揉め易い事柄です。
これらの負担方法について、予め婚前契約書に明確に定めておけば、万が一、別居や離婚協議に至った場合にも、婚前契約書の定めに従って負担することになりますので、無用な争いを回避できる可能性が高まります。
そこで、今回は、婚前契約における婚姻費用、養育費についてご説明します。
そもそも婚姻費用、養育費とは
民法は、
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています(民法第760条)。
また、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とも規定しています(民法第752条)。
このように夫婦は、お互いに扶養し合う義務があり、共同して生活するための費用(婚姻費用)を協力して負担しなければならないと規定されています。
婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子供の教育費など夫婦が共同して生活するうえで必要な一切の費用をいいます。婚姻費用には、子供の養育費も含まれ、離婚後は、夫婦間の扶養義務はなくなり、子に対する扶養義務のみが残りますので「婚姻費用」ではなく、「養育費」ということになります。
なお、養育費は、未成熟子を扶養するための費用です。未成熟子とは、経済的に独立して自分の生活費を稼ぐことができない子供をいいますので、未成年であっても既に働いており、その収入で生活できる子供に対しては養育費を支払う義務はなくなります。
婚姻費用、養育費の金額はどのように決まるのか
総収入(源泉徴収票の「支払金額」、確定申告書の「課税される所得金額」)から、税金や住居費などの経費を控除した「基礎収入」という金額を算出し、さらに子供の年齢や人数を考慮して婚姻費用、養育費の金額は算定されます。これを標準的算定方式といいます。
婚姻費用や養育費の金額の概算を簡単に知る方法として、裁判所が作成した「婚姻費用・養育費算定表」を用いる方法があります。
婚前契約書における婚姻費用の定め方
婚姻費用の金額について、どのように盛り込むべきか
婚前契約書は結婚前に作成するものですから、長い結婚生活の中で、夫婦それぞれの収入や子供の有無・人数は変化します。
ですから、「毎月○○万円の婚姻費用を支払う」というように一定の金額を記載すると、将来、その金額が高すぎる、あるいは低すぎる事態になることが予想されます。
そこで、収入や扶養すべき子の変化に対応できるよう裁判所の算定表に従って計算することを婚前契約書に定めることが考えられます。
もっとも、算定表の婚姻費用の金額には幅がありますので、その幅の中でいずれの金額にするか揉める可能性が高いです。そのため、婚前契約書には、一義的に金額が決まるように、計算式を記載する又は裁判実務で採用されている標準的算定方式に従うと記載すると良いでしょう。
また、裁判実務では、幼児がおり妻が働いていない場合にも、平均的なパート収入程度は収入を得ることができると仮定して、妻の収入がゼロの場合よりも婚姻費用の金額が低く算定されることが多くあります。そこで、婚前契約において、そのような場合の妻の収入はゼロとして計算すると定めることも考えられます。
同居中の婚姻費用の負担方法についても盛り込むべきか
夫婦関係が良好な状態の婚姻費用の負担方法については、敢えて婚前契約書に盛り込む必要はないのではないかとも思えますが、生活費の負担方法について予め決めておくことで、無用な喧嘩を避けることを期待できます。
別居後の婚姻費用の負担方法はどのように定めるべきか
別居後は婚姻費用を一切負担しないという定めを設けることも考えられますが、夫婦の扶助義務を一律に否定するこのような取り決めは、法的に無効となる可能性があります。
他方、別居後、夫婦関係が修復される余地も、そのための努力も一切なされなくなった状態になっても、離婚するまでずっと婚姻費用を負担し続けなければならないのが酷な場合もあるでしょう。
そこで、婚姻費用の支払期間について、例えば、別居期間が1年を超えた場合には、婚姻費用の負担義務を免除する規定を置くことが考えられます。但し、婚姻費用を負担する義務者の不貞や暴力が原因で別居に至った場合には、このような規定の法的効力は否定されるでしょう。
また、別居期間が長くなるにつれて、夫婦関係の破綻している程度はどんどん大きくなっていきますので、例えば、別居開始から半年以内、半年から1年、1年から2年と期間が長くなるにつれて負担するべき婚姻費用の金額を低下させていき、数年後には支払義務を免除するような規定を盛り込むことも考えられます。
このように婚姻費用の支払いを制限する規定を婚前契約書に定めることが考えられますが、夫婦間の扶助義務は法律が定める義務のため、別居時において夫婦がともに十分な所得があり婚姻費用の支払いがなくとも十分に生活できる場合であればともかく、そうでなければ法的に無効となる可能性があることは留意する必要があります。
なお、婚姻費用のうち養育費に相当する金額については、子の利益を侵害することになりますので、上記のような制限をしても法的効力は否定されます。
婚前契約書における養育費の定め方
養育費の金額について、どのように盛り込むべきか
養育費の金額についても、先ほどご説明しました婚姻費用の金額と同じく、一義的に決まるよう、婚前契約書には計算式を記載する又は裁判実務で採用されている標準的算定方式に従うと記載すると良いでしょう。
何歳まで養育費を負担するのか?学費の負担はどうするのか?
養育費の負担は20歳までというのが一般的です。
そもそも養育費は、経済的に独立して自分の生活費を稼ぐことができない子供を扶養するための費用です。20歳になって成人になれば、自分で生活費を稼ぐことができるだろうと考えられることから、養育費の負担は20歳までとされることが一般的でした。
しかし、国民の半分以上が4年生大学に進学している現状を考えると、養育費の負担を20歳までとすることに合理性はないようにも思えます。他方、中学校や高校を卒業した後、進学せずに就職して、自立する子も多くいます。
そこで、養育費の負担については、子の年齢で終期を定めるのではなく、子が就職する前月まで、あるいは、高校、大学に進学した場合には卒業する月までと定めるのが良いでしょう。
学費の負担はどうするのか?
算定表や、その元となる計算式から算出される養育費には私立学校の学費は考慮されていませんし、大学の学費も考慮されていません。そのため、婚前契約書には、これらの学費の負担についても定めることが考えられます。
もっとも、例えば、学費は全て負担すると規定したからといって、私立の医学部のように高額な学費がかかる場合にまで全てを負担することは想定していないかもしれません。ですから、学費を負担すると定める場合にも、上限を定めたり、協議できる余地は残しておくべきでしょう。
また、親権者となった前配偶者が再婚したり、事実婚状態になった場合には、仮にその相手と子が養子縁組をしていなかったとしても養育費の支払義務を免除すると定めることが考えられます。
この場合、普段の生活費については再婚相手が負担してくれるでしょうが、学費については負担をしてくれないかもしれませんので、学費については負担すると定めておくことも検討の余地があります。
最後に
以上、婚前契約における婚姻費用、養育費の定め方について見てきました。
婚前契約書は、円満な夫婦関係を持続するための契約書と考えるべきものですが、夫婦関係が崩れ、別居、離婚に至った際に大きな効力を発揮することも間違いありません。
<p>結婚する前から別居や離婚を考えるのは気持ち良いことではありませんが、万が一のときに無用な争いを避けるために、予め婚前契約書に定めておくことを強くお勧めします。
ご自身たちに合った婚姻費用、養育費の負担方法を定めるためには、婚前契約書に詳しい弁護士にご相談ください。
以下のコラムもご覧ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。