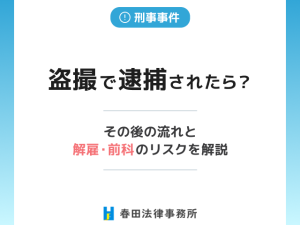【盗撮の余罪】バレる可能性は?弁護士が解説する捜査と対処法
最終更新日: 2025年11月22日
もしご自身が盗撮の容疑で警察の捜査対象となり、過去の他の盗撮行為まで発覚するのではないかと、言いようのない不安に苛まれているのであれば、この記事はあなたのためのものです。この状況では、多くの方が「自分のデータは大丈夫だろうか」「警察にどこまで調べられるのか」と、途方に暮れていることでしょう。
本記事では、盗撮の余罪が警察に発覚する可能性について、スマートフォンのデータ解析や供述、家宅捜索といった具体的な捜査手法を交えながら、弁護士の視点から詳しく解説いたします。さらに、余罪が発覚した場合の刑事手続きの流れや、それが最終的な処罰にどう影響するのか、そして最悪の事態を避けるために今すぐ取るべき具体的な対処法についても、冷静かつ専門的なアドバイスを提供します。あなたの不安に寄り添いながら、未来に向けて最善の選択ができるよう、この記事がその一助となることを願っています。
春田法律事務所
弁護士に相談する初回無料
盗撮の余罪がバレるか不安…スマホのデータは大丈夫?
盗撮事件で警察に検挙された方が最も大きな不安として抱えるのは、ご自身のスマートフォンやパソコン、その他のデジタル機器に残された過去の盗撮データ(余罪)が警察に発見されてしまうのではないか、という点ではないでしょうか。多くの方が「データを削除したから大丈夫だろう」「端末を初期化すれば見つからないはずだ」と安易に考えがちです。しかし、残念ながらその認識は必ずしも正しいとは言えません。
現代の警察は、デジタル証拠の解析に関して非常に高度な専門技術を有しています。たとえあなたがデータを自力で削除したとしても、専門の捜査機関による「デジタル・フォレンジック」と呼ばれる技術を駆使すれば、消去されたはずのデータが復元され、過去の盗撮行為が次々と明らかになるケースが後を絶ちません。復元された画像や動画からは、撮影日時、場所、そして時には被害者の特定に繋がる情報までが詳細に分析されます。
このように、安易なデータ削除は無意味であるばかりか、かえって証拠隠滅を図ったと判断され、あなたにとって極めて不利な状況を招く可能性があります。あなたの抱える「余罪がバレるかもしれない」という不安は、決して杞憂ではないのです。続くセクションでは、こうした余罪が具体的にどのように発覚するのか、さらに詳しく解説していきます。
そもそも盗撮事件における「余罪」とは?
刑事事件における「余罪」とは、現在捜査の対象となっている特定の犯罪行為(これを「本件」と呼びます)とは別に、被疑者が過去に犯した他の犯罪を指す言葉です。法律用語として明確に定義されているわけではありませんが、実務上、警察や検察が捜査を進める中で明らかになる、別の犯罪行為全般を指すものとして使われます。
盗撮事件においては、例えばあなたが今、ある特定の盗撮行為で警察に事情聴取を受けているとします。この「本件」とは別に、あなたのスマートフォンやパソコン、あるいはクラウドストレージなどに保存されている他の盗撮データ、あるいはあなたが過去に友人や知人に話した内容から発覚する別の盗撮行為などが「余罪」に該当します。これらは、時期や場所、被害者が異なる場合でも、あなたが関与した盗撮行為であれば全て余罪とされ得ます。
余罪が発覚すると、警察や検察は本件とは別にその余罪についても捜査を進めます。場合によっては、新たな証拠が見つかるたびに、別件として再逮捕されたり、本件と併せて新たな刑事事件として立件されたりする可能性があります。つまり、単に罪の数が増えるだけでなく、捜査が長期化し、あなたの身体拘束も長期にわたるリスクがあることを意味します。
盗撮の余罪がバレる可能性|捜査で発覚する3つのきっかけ
警察などの捜査機関は、ある犯罪で被疑者を検挙した場合、他にも同様の犯罪を行っている可能性を常に視野に入れて捜査を進めます。特に盗撮は常習性が高い犯罪であるため、本件の捜査と並行して余罪がないかの確認が厳しく行われる傾向があります。そのため、「今回は運悪く見つかっただけだろう」と考えていると、思わぬ形で過去の盗撮行為が発覚し、事態が深刻化するケースが少なくありません。
盗撮の余罪が警察に発覚する主なきっかけは、次の3つです。一つ目は、押収されたスマートフォンやパソコンの徹底的な解析、二つ目は、被疑者自身の取り調べでの供述、そして三つ目は、家宅捜索による証拠品の発見です。それぞれのきっかけについて、以下で詳しくご説明します。
スマホやPCの解析・データ復元
盗撮の余罪が発覚するきっかけとして最も一般的で、かつ発覚の可能性が高いのが、警察によるデジタルデバイスの徹底的な解析です。盗撮事件で逮捕・検挙されると、まず間違いなく犯行に使用されたスマートフォンが押収されます。警察には「デジタル・フォレンジック」と呼ばれる高度な専門技術を持つ部署があり、押収されたデバイスの内部データを隅々まで解析します。
この技術は非常に高度であり、仮に被疑者自身がデータを削除したり、端末を初期化したりした場合でも、多くの場合、データは復元されてしまいます。「削除したから大丈夫だろう」という考えは通用しないのが実情です。復元された画像や動画データからは、撮影日時、場所、GPS情報などが詳細に特定されることがあり、これらの情報から新たな被害者が割り出され、本件とは別の余罪として次々と立件されることになります。証拠隠滅を試みても無駄に終わるだけでなく、その行為自体が罪を重くする不利な情状となるため、絶対に避けるべきです。
被疑者自身の供述
取り調べにおいて被疑者自身の供述が、余罪発覚のきっかけとなるケースも少なくありません。警察官や検察官は、豊富な経験とテクニックを駆使して取り調べを進めます。捜査官からの執拗な追及や説得、あるいは被疑者自身の罪悪感から、過去の他の盗撮行為を自ら打ち明けてしまうことがあります。
特に、押収されたスマートフォンからデータが見つかった後、「他にも何かあるだろう」「正直に話せば情状酌量の余地もある」などと追及され、観念して余罪を全て話してしまうパターンが多く見られます。また、反省の態度を示すために自発的に余罪を申告するケースもありますが、それが必ずしも有利な結果につながるとは限りません。供述の内容は、その後の刑事手続きや最終的な処罰に大きく影響するため、安易な供述は避けるべきです。
家宅捜索による証拠品の発見
盗撮事件においては、裁判所の令状に基づき、被疑者の自宅に対して家宅捜索が実施されることがあります。これは、犯行に使われたスマートフォンだけでなく、過去の盗撮データ(余罪)が保存されている可能性のある他の証拠品を発見するためです。家宅捜索では、古いスマートフォン、パソコン、外付けハードディスク、SDカード、USBメモリなど、あらゆる記録媒体が押収の対象となります。
これらのデバイスが警察に押収され、デジタル・フォレンジックによって解析される中で、被疑者自身も存在を忘れていたような過去の盗撮データが次々と発見されることがあります。これにより、本件とは別の多数の余罪が明らかになり、さらなる捜査や再逮捕へとつながる可能性が高まります。自宅にデジタルデバイスを多数保管している方は、家宅捜索のリスクとそこから余罪が発覚する可能性を十分に認識しておく必要があります。
盗撮の余罪が発覚するとどうなる?処罰への影響と捜査の流れ
盗撮事件において余罪が発覚した場合、被疑者の方にとってはその後の刑事手続きや最終的な刑事処分に非常に大きな影響が及ぶ可能性があります。単に罪の数が一つ増えるという問題にとどまらず、捜査の長期化、身柄拘束期間の延長、そして最終的な刑罰の加重といった、極めて不利な状況を招きかねません。このような状況は、被疑者の社会生活に甚大な影響を与え、職場やご家族との関係にも深刻な事態をもたらす恐れがあります。このセクションでは、余罪が発覚した際に具体的にどのような事態が起こりうるのか、再逮捕や追起訴の可能性、そして量刑への具体的な影響について詳しく解説します。
余罪が立件され再逮捕・追起訴される可能性がある
盗撮事件で余罪が発覚した場合、もっとも懸念されることの一つが「再逮捕」や「追起訴」です。最初に逮捕された事件(本件)で身柄を拘束されている間に、警察は押収したスマートフォンやパソコンのデータ解析を進め、別の盗撮行為の証拠を発見することがあります。このとき、もし余罪の証拠が固まると、その余罪を理由に再度逮捕される可能性があります。これを「再逮捕」と呼び、再逮捕されるとさらに最大20日間の身柄拘束が続くことになり、結果として身体拘束が大幅に長期化してしまいます。
身柄拘束が長期化すると、会社を長期に休まざるを得なくなり、職場に事件が発覚するリスクが高まるほか、ご家族への精神的な負担も大きくなります。その後、検察官は本件と余罪を合わせて起訴するか(追起訴)、あるいは別々の事件として起訴するかを判断します。いずれにしても、余罪が立件されるということは、身体拘束の長期化や刑事手続きの複雑化に直結するため、被疑者にとって非常に厳しい状況となるのです。
刑罰が重くなる|併合罪と量刑への影響
複数の盗撮行為、つまり余罪が立件された場合、最終的に科される刑罰は当然のことながら重くなる傾向にあります。これは、刑法上の「併合罪(へいごうざい)」という考え方が適用されるためです。併合罪とは、確定裁判を経ていない複数の犯罪行為がまとめて審理される場合に適用されるもので、この場合、最も重い罪の刑罰を基準に、その長期(最長期間)が1.5倍まで加重される可能性があります。
例えば、それぞれ懲役3年が上限の罪が複数あったとしても、単純に「3年+3年」と刑期が合算されるわけではなく、「3年×1.5倍=最大4年6ヶ月」といった形で刑罰が重くなる可能性があるのです。また、法律上の規定だけでなく、裁判官が量刑を判断する際の「情状」面においても、多数の余罪があるという事実は極めて不利に働きます。「常習性が高い」「反省が見られない」「犯情が悪質である」などと評価され、結果としてより厳しい判決が下される傾向にあります。余罪の存在は、単に罪が増えるというだけでなく、その量刑にも大きな影響を与えるため、決して軽視できない問題です。
余罪が立件されにくいケースとその理由
すべての盗撮の余罪が必ずしも立件されるわけではありません。中には、警察が余罪を把握していても、さまざまな事情から立件が見送られるケースも存在します。主に以下の3つの理由が挙げられます。
一つ目は、被害者の特定が困難な場合です。例えば、画像や動画から被害者の顔や身元が判明しない場合、被害届が出されることが難しく、事件として立件することができません。二つ目は、犯罪の証明が困難な場合です。撮影された映像が、現在の「性的姿態撮影等処罰法」や各都道府県の迷惑防止条例の構成要件を満たしているかどうかの判断は非常に厳格です。たとえば、着衣の全身像のみで、直ちに性的羞恥心を害する行為とは断定できないようなケースでは、立件が見送られることがあります。三つ目は、公訴時効が完成している場合です。刑事事件にはそれぞれ公訴時効が定められており、その期間を過ぎてしまうと、たとえ犯罪の事実があったとしても起訴することができません。
しかし、これらの判断は個別の事情によって大きく異なり、最終的には検察官の判断に委ねられます。「立件されないだろう」と安易に自己判断するのは非常に危険です。たとえ立件に至らなくても、取り調べで余罪が追及されることで本件の情状に悪影響を及ぼす可能性も十分に考えられます。
盗撮の余罪がバレるのを恐れて…やってはいけないNG行動
盗撮の余罪発覚を恐れる気持ちは痛いほどよくわかります。しかし、その不安な気持ちから焦って誤った行動を取ってしまうと、事態をさらに悪化させ、取り返しのつかない結果を招く可能性があります。ここでは、パニックに陥った時にうっかりやってしまいがちな、しかし絶対に避けるべきNG行動について解説します。具体的には、証拠隠滅を目的としたスマホのデータ削除や初期化、取り調べでの安易な黙秘や嘘の供述、そして被害者への直接連絡などが挙げられます。これらの行動がなぜ危険なのかを理解し、冷静な判断を心がけることが大切です。
証拠隠滅|スマホのデータを削除・初期化する
余罪の発覚を恐れてスマートフォンやパソコン内のデータを削除したり、端末を初期化したりする行為は、多くの方が考えてしまいがちですが、これは非常に危険なNG行動です。確かにデータは一時的に見えなくなりますが、警察の「デジタル・フォレンジック」と呼ばれる高度な専門技術をもってすれば、一度削除されたデータも高確率で復元されてしまいます。つまり、証拠隠滅の試みはほとんどの場合が無駄に終わるだけでなく、事態をさらに悪化させる要因となります。
それどころか、証拠を隠そうとしたという事実自体が、捜査機関や裁判所から「反省していない」「悪質である」と判断され、被疑者にとって極めて不利な情状として考慮されます。その結果、逮捕の必要性が高まったり、最終的な量刑が重くなったりする可能性が非常に高まります。場合によっては「証拠隠滅罪」という別の犯罪が成立してしまうリスクまでありますので、絶対に手を出してはならない行動です。
安易な黙秘や嘘の供述をする
警察官や検察官からの取り調べは、精神的なプレッシャーが大きく、つい嘘をついたり、弁護士に相談しないまま安易に黙秘権を行使したりしてしまうケースがあります。しかし、嘘の供述は、スマートフォンに保存されたデータなどの客観的な証拠と矛盾が生じ、すぐに発覚してしまうものです。一度嘘が明らかになると、供述全体の信用性が失われ、その後の真実の供述さえも信じてもらえなくなります。そうなると、「反省していない」「捜査に非協力的である」と見なされ、結果的に被疑者にとって非常に不利な状況に陥ってしまいます。
また、黙秘権は被疑者に認められた重要な権利ですが、その行使には高度な戦略的判断が求められます。弁護士のアドバイスを受けずに、ただ不自然に黙秘を貫いてしまうと、かえって捜査機関の疑いを強め、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて身体拘束が長期化する原因となりかねません。自己判断での安易な黙秘や嘘の供述は避け、必ず弁護士に相談して適切な対応方針を立てることが重要です。
被害者へ直接連絡し示談しようとする
発覚した事件や余罪について、「自分で被害者に直接連絡を取って示談をすれば、早く解決するのではないか」と考えてしまう方もいらっしゃいます。しかし、これは絶対に避けるべきNG行動です。加害者本人からの突然の連絡は、被害者にとってさらなる恐怖や精神的苦痛を与え、事態を一層悪化させる可能性が極めて高いです。被害感情を逆なでし、警察や検察への通報を促してしまうことにもつながりかねません。
さらに、加害者本人からの連絡は、警察や検察から「口封じ」や「脅迫」と受け取られ、「証拠隠滅を図っている」と判断されるリスクがあります。その結果、本来であれば逮捕されずに済んだかもしれない事件で逮捕に至ったり、示談交渉そのものが完全に決裂してしまったりといった最悪のケースも十分に考えられます。被害者とのコンタクトや示談交渉は、必ず弁護士を代理人として通し、冷静かつ誠実に対応することが不可欠です。
盗撮の余罪が発覚した場合の正しい対処法|弁護士に相談が不可欠
もしも盗撮の余罪が発覚してしまった、あるいはその可能性に不安を感じているのであれば、最も重要なのは一刻も早く弁護士に相談することです。パニックに陥り、不適切な行動を取ってしまう前に、刑事事件の専門家である弁護士の助言を仰ぐことが、事態の悪化を防ぎ、冷静に対処するための唯一の方法と言えます。弁護士に相談することで、身体拘束の回避、刑事処分の軽減、そして最終的な社会復帰への道筋を見つけるための具体的な一歩を踏み出すことができます。このセクションでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットとして、取り調べへの適切な対応、被害者との示談交渉、そして再犯防止に向けた具体的な取り組みについて詳しく解説します。
取り調べへの対応方針についてアドバイスを受ける
弁護士に相談する大きなメリットの一つは、警察や検察による取り調べに対して、どのように対応すべきかについて具体的なアドバイスを受けられる点です。弁護士は、被疑者の状況を詳細にヒアリングし、法的に有利となる点と不利となる点を整理した上で、供述すべき内容や、場合によっては黙秘権を行使すべき内容について具体的に指示してくれます。これにより、意図せず自分に不利な供述調書が作成されてしまうことを防ぎ、被疑者の権利が不当に侵害されることを避けることができます。
また、取り調べの際に作成される供述調書は、後の裁判で重要な証拠となるため、その内容をしっかり確認し、納得できない部分には決して署名・押印しないという実践的な助言も得られます。弁護士という法的な味方がいることは、精神的なプレッシャーを大きく軽減し、冷静な判断力を持って取り調べに臨むことにも繋がります。こうした専門家からのサポートは、孤独な状況に置かれがちな被疑者にとって、非常に心強い支えとなるでしょう。
被害者との示談交渉を弁護士に依頼する
弁護士に依頼する最大のメリットの一つに、被害者との示談交渉を代理してもらえる点が挙げられます。捜査機関は、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。そのため、被害者との示談交渉を進めるためには、弁護士のような第三者が間に入るのが不可欠となります。
弁護士が代理人として交渉にあたることで、被害者の方の警戒心を和らげ、冷静な話し合いのテーブルについてもらえる可能性が高まります。また、弁護士は適切な示談金の相場を把握しており、双方にとって納得のいく条件での示談成立を目指してくれます。もし「加害者を許す」という宥恕(ゆうじょ)文言付きの示談が成立すれば、それは不起訴処分の獲得や、起訴された場合の刑の軽減に極めて有利に働く重要な材料となります。被害者の心情に配慮しつつ、迅速かつ適切な示談交渉を進めることが、事件解決への近道となります。
再犯防止に向けた具体的な取り組みを始める
刑事手続きにおいては、単に反省の言葉を述べるだけではなく、再犯防止に向けた具体的な行動を示すことが極めて重要です。弁護士は、被疑者の方の状況を詳細に把握した上で、裁判官や検察官が評価する有効な再犯防止策についてアドバイスしてくれます。
例えば、性依存の治療を専門とする医療機関への通院、盗撮行為に繋がるようなウェブサイトへのアクセスを物理的に遮断するためのスマートフォンへのフィルタリングアプリの導入、さらには家族による定期的な監督体制の構築などが挙げられます。これらの具体的な取り組みを意見書としてまとめ、検察官や裁判官に提出することで、本人が真摯に更生しようと努力していることを客観的に示すことができます。こうした積極的な姿勢は、寛大な処分を求める上で非常に強力な材料となり、社会復帰への道を拓くことにも繋がるでしょう。
盗撮の余罪に関するよくある質問
このセクションでは、盗撮の余罪に関して多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。
Q. 削除した盗撮データは警察に復元されますか?
はい、高い確率で復元されます。警察は「デジタル・フォレンジック」と呼ばれる高度な専門技術を用いて、スマートフォンやパソコンの内部データを徹底的に解析します。削除されたデータであっても、多くの場合、専用のツールを使うことで復元が可能です。安易なデータ削除は無意味であるばかりか、証拠隠滅を試みた行為と見なされ、逮捕の必要性が高まったり、最終的な量刑が重くなったりするなど、かえって不利な状況を招くリスクがあるため、絶対に避けるべきです。
Q. 押収されたスマートフォンはいつ返ってきますか?
押収されたスマートフォンの返還時期に明確な決まりはありませんが、捜査が終了し、事件が終結するまで返還されないのが一般的です。具体的には、不起訴処分が決定した時点や、起訴されて裁判が終了した時点が目安となります。ただし、裁判で重要な証拠品として提出された場合、そのまま返還されない(領置される)こともあります。ご自身で還付請求(返還を求める手続き)を行うこともできますが、弁護士を通じて「還付請求」を速やかに行うことで、早期返還の可能性を探ることができます。
Q. 家族や会社にバレずに解決することは可能ですか?
家族や会社に知られずに事件を解決することは、不可能ではありませんが、状況によってその可能性は大きく異なります。最も大きな分かれ目となるのは「逮捕されるかどうか」です。逮捕されてしまえば、通常、家族に連絡が入ったり、長期の欠勤により会社に知られたりする可能性が非常に高まります。そのため、早期に弁護士へ依頼し、逮捕を回避するための活動(自首への同行や、捜査機関への意見書提出など)を行うことが、秘密裏に解決できる可能性を高める鍵となります。弁護士は、あなたの状況に応じて最も適切な対応をアドバイスし、社会生活への影響を最小限に抑えるよう尽力します。
Q. 弁護士に相談する費用はどのくらいかかりますか?
弁護士費用は法律事務所や事案の複雑さによって異なりますが、多くの事務所では初回相談料が無料、または30分5,000円程度の費用で設定されています。正式に弁護を依頼する場合は、主に「着手金」と「報酬金」の2段階で費用が発生することが一般的です。盗撮事件の場合、着手金は30万円から50万円程度が相場とされています。報酬金は、不起訴処分の獲得や刑の軽減といった成果に応じて発生する費用です。まずは複数の法律事務所に相談して、ご自身のケースでの見積もりを確認することをおすすめします。
まとめ:盗撮の余罪は早期に弁護士へ相談し、社会生活への影響を最小限に
盗撮事件で警察の捜査対象となり、「過去の他の盗撮もバレるのではないか」と不安を抱えている方は、その余罪が発覚するリスクが非常に高いことを認識しておく必要があります。スマートフォンやパソコンの高度な解析技術により、削除されたデータであっても復元され、再逮捕や起訴、そして最終的な刑罰の加重といった深刻な結果を招く可能性は決して低くありません。余罪が発覚すれば、本件とは別に刑事手続きが進められ、長期の身体拘束や社会生活への甚大な影響は避けられなくなるでしょう。
このような状況に直面した際に、最も重要なのはパニックに陥って不適切な行動を取らないことです。証拠隠滅を試みたり、安易な黙秘や嘘の供述をしたりすることは、事態をさらに悪化させ、かえって不利な情状として評価されてしまいます。また、被害者へ直接連絡することは、証拠隠滅や脅迫とみなされるリスクがあるだけでなく、被害者の心情をさらに傷つけ、示談の可能性を閉ざしてしまうことにもつながりかねません。
したがって、盗撮の余罪が発覚した、あるいはその可能性がある場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、警察の取り調べに対する適切な対応方針をアドバイスし、不当な供述調書の作成を防ぎます。また、被害者との示談交渉を代理することで、冷静かつ円滑な解決へと導き、不起訴処分の獲得や刑の軽減に尽力します。さらに、再犯防止に向けた具体的な取り組みを検討し、真摯な反省を客観的に示すことで、より良い刑事処分を得るための重要な材料となります。弁護士に早期に相談し、適切な対処を講じることが、身体拘束を回避し、最終的な刑事処分を軽くし、社会生活への影響を最小限に抑えるための唯一の道だと言えるでしょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
春田法律事務所
弁護士に相談する初回無料