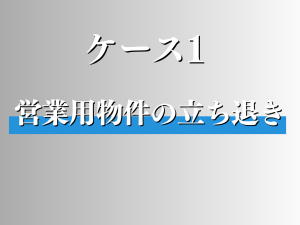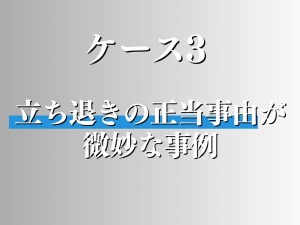立退料は賃貸借契約書が全て!?弁護士が賃貸人・賃借人の抑えるべき注意点をケースで解説
最終更新日: 2023年11月23日
立退料の交渉において、賃貸借契約書の「立退料を請求できない」定めが争点になることがあります。賃貸人としては、契約書に明記されていることなのだから、賃借人は当然守るべきと考えるでしょう。
他方、賃借人としては、契約当時、「立退料を請求できない」という条項をよく読んでいなかったかもしれませんし、たとえ当該条項のことをわかっていたとしても、何らの補償もなく退去することに抵抗を覚えるかもしれません。
実は、借地借家法という法律が、賃借人を保護するために賃貸借契約の内容を一部修正する場合があります。「立退料を請求できない」旨の条項があったとしても、必ずしもそのとおりに効力が維持されるとは限らないのです。
今回、専門弁護士が、「立退料を請求できない」旨の条項について、法的効力のある賃貸借契約書とそうでない賃貸借契約書の違いを、賃貸人と賃借人のそれぞれの立場から解説します。
賃貸借契約書と立退料を巡る相談を専門の弁護士が解説
立退料に関する相談には、賃貸借契約書の記載内容の解釈方法に関して争いが生じることが多いです。
立退料を請求できなくする賃貸借契約書の記載が、具体的な事案においてどのように扱われるのか、基本的な考え方を見ていきましょう。
立ち退きには正当事由が必要
まず、賃借人を立ち退かせるためには、賃貸人に建物使用の必要性という正当事由が必要です(借地借家法28条)。
この正当事由が認められるためには、単に、賃貸人において、建物を使用する具体的予定があるというだけでは足りず、賃借人の建物使用の必要性を明らかに上回ることまで求められます。
言い換えるなら、賃貸人の必要性が賃借人の必要性と同程度で、甲乙つけがたいという状態では、「明らかに上回る」とは認められず、正当事由がないとの判断になります。
ただ、それでは賃貸人の正当事由がクリアできるケースが極めて少なくなってしまうので、正当事由を補強する要素として、立退料の支払うことでの解決が図られるようになりました。
そのため、現在の裁判実務では、多くのケースにおいて、立退料を支払わなければ、賃貸人の正当事由が肯定されないのが現状となっています。
賃貸借契約書は賃貸人を有利にする?
賃貸人としては、賃借人を立ち退かせるにあたり立退料を支払いたくないと考えるのが通常ですから、立退料を排除するため、賃貸借契約書に様々な規定を盛り込みます。代表的な規定としては、「賃借人は、退去するにあたり、立退料を一切請求しない」という内容のものです。
では、このような賃貸人有利の規定は、有効なのでしょうか。
借地借家法30条において、「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」規定があるため、この規定に抵触する賃貸借契約書の規定は効力を失うことになります。
そのため、賃貸借契約書に賃貸人に有利な規定を盛り込んでいても、必ずしも賃貸人を有利にするわけではありません。
賃借人が立退料を請求できなくなる条件は?
他方で、賃借人の立場からしますと、借地借家法30条があるから、どんなに不利な条件で合意したとしても、無効にできると思われるかもしれません。
確かに、借地借家法30条の規定は、かなり適用範囲が広く、借地借家法を骨抜きにするような不当な条項の多くを無効化してきました。しかしながら、いかなる場合においても、借地借家法30条によって立退料不払いの条項が無効になるとは限らないのです。
たとえば、賃借人に家賃不払いなど債務不履行がある場合、立退料を請求できないとの条項が定められていることがあります。これは、法的には、債務不履行解除となるため、借地借家法30条の問題とはなりません。債務不履行解除が認められると、賃借人は、立退料が支払われることなく、退去に応じなければなりません。
また、定期借家契約の場合には、借地借家法30条の適用は排除されています(借地借家法38条)。そのため、定期借家契約が終了し、賃貸人より「再契約」の提案がない場合、立退料を請求することもできず、退去に応じなければなりません。
さらに、賃借人の保護が十分にされた上で賃借人が立退料の不払いに合意している場合など、賃借人にとって「不利」とは認めらない場合にも、借地借家法30条の適用はありません。
賃貸人が立退料について契約書で押さえるべき注意点
賃貸人にとって、どれほど有利な条件で契約をしたとしても、借地借家法によって無効となっては意味がありません。賃貸人としては、借地借家法に抵触しないよう、賃貸借契約書を作成する必要があります。
まずは賃貸人の立場で押さえるべきポイントを確認していきましょう。
賃貸借契約書を締結する際
前述したとおり、賃貸借契約書には、借地借家法に反するような定めはできません。普通借家契約において、賃貸人の一方的都合によって、立退料の支払いもなく、賃借人を退去させることは困難と考えてよいでしょう。
もし、期間が満了したら、確実に退去させたいのであれば、定期借家契約にするしかありません。
更新契約書を締結する際
更新契約書を作成する際、今回の更新契約の期間満了をもって契約終了となり、更新はしない旨の定めを明記しておくことがあります。
しかしながら、賃貸借契約の更新はない旨の規定は、更新拒絶等の制限に関する規定に正面から違反するので借地借家法30条で無効とされるリスクが高く、注意が必要です。
賃貸人としては、賃借人と感情的な対立が生じる前に、定期借家契約への切り替えの提案をしたり、期限付合意解約の方向で賃借人と条件を調整することが望ましいといえます。
立ち退き合意を締結する際
せっかく賃借人が建物からの立ち退きに合意するのですから、実効性のある合意書を作成するべきです。
立ち退きの期限が、不確定な期限にかかってしまうと、結局、賃借人としてはいつまでに退去すれば良いのかわからなくなり、立ち退きそのものが実現できなくなる可能性もあります。
また、立ち退き合意書を作成し、立退料まで支払ったにもかかわらず、やはり立ち退きに納得できないとして、賃借人が居座ることもあります。
この場合、裁判をしないと賃借人を退去させることができないので、賃借人において自発的に出ていくような工夫が必要となります。たとえば、退去を確認した後に、立退料を支払うなどの条件を設定しておくことも有用です。
賃借人が立退料について契約書で押さえるべき注意点
借地借家法によって最低限の権利を保障されているとしても、賃借人においても、当然、押さえるべきポイントはありますので、いくつか確認しておきましょう。
賃貸人が大手の不動産会社の場合
賃貸人が大手の不動産会社であったりすると、借地借家法に則った契約書がほとんどなので、契約時に気を付ける点はそれほど多くありません。
ただ、最近は、首都圏を中心に定期借家契約を締結する事案も増えています。定期借家契約は、更新がなく、賃貸人の一方的な更新拒絶があっても立退料を請求できなくなるため、契約時に注意するべきです。
賃貸人が個人の場合
立ち退きのトラブルになる紛争では、借地借家法に明らかに違反するような内容があり、賃貸借期間、賃料の支払方法の記載事項があいまいになっている契約書が散見されています。
契約書の取り決めがあいまいになると、賃貸人との間で契約内容の認識についてずれが生じます。そして、その契約内容に関する認識のずれが対立を生み、立退料の交渉を困難にしています。
契約書の締結時には、契約期間、賃料の支払方法など、あいまいな記載になっていないかを確認しておくべきでしょう。
契約書で定めた内容が立退料交渉に与える影響
一般の賃貸人と賃借人が、専門弁護士と同等の知識を有していることは稀であることから、契約書の文言について、各自が自身の判断基準に従った解釈をして、交渉を進めようとします。
それぞれ、具体的なケースごとに見ていきましょう。
よくある契約書の記載事項が問題となったケース
よくある例として、賃貸借契約書に「賃借人は立退料を一切請求できない」旨の記載があることから、賃貸人が全く立退料を提示せず、賃借人と深刻なトラブルに陥るケースです。
前述したとおり、借地借家法28条が存在しますから、賃貸人の一方的な都合で、立退料の支払もなく、無条件での明渡しを賃借人に強制するのは困難です。この場合、一切立退料を支払わなくてよい旨の賃貸人の解釈は、誤っている可能性が極めて高いといえます。
もっとも、賃借人によっては、立退料を請求できない条件で合意してしまっているからと誤解して、無条件の退去に応じてしまう方も多くいらっしゃいます。突然、住む場所を追われてしまうのではないかと不安になり、賃貸人ともめる前に、別の部屋を探す時間的余裕があるうちに退去しようと考えてしまうのでしょう。
たしかに、立ち退き要求を無視することは、勇気がいることですが、そのような場合にこそ、賃借人の権利を守るために借地借家法が存在します。
まずは、一度冷静になって、正当な立退料を支払ってもらえるよう、毅然と交渉する態度が必要ですし、自身で判断できない場合には弁護士に対応を相談するべきです。
立退料を放棄する誓約書を差し入れたケース
次に、問題となるのが、契約更新のタイミングで、次回は更新をしないとのことで、予め契約終了時までに立ち退く旨の誓約書を賃借人から取り付けているケースです。
賃借人の立場からしますと、更新契約の時点では、特に問題ないと思って誓約書にサインしたものの、更新した契約の満了前になってみて事情が変わり、簡単に立ち退くことができない状況に陥ることがよくあります。
しかしながら、賃貸人の立場からすれば、誓約書まで差し入れているのに立ち退きに応じず、立退料まで求められると、たまったものではありません。この場合、賃貸人と賃借人間の感情的な対立はかなり強く、立退料交渉も困難な事案になるといえるでしょう。
では、このような場合、誓約書の効力はどのように判断されるのでしょうか。
このように明渡し期限が不確定条件にかかっているような場合、賃借人が誓約書を差し入れていたとしても、借地借家法の適用を排除することはできない可能性が高いです。不確定条件となると、明渡し期限は、1年後かもしれませんし、10年後かもしれませんので、賃借人は不安定な立場に置かれるからです。
ただし、誓約書の存在によって、正当事由の判断について賃貸人に有利な解釈がとられる可能性が高まります。その意味では、誓約書を差し入れてもらうことが、全く無意味であるとまではいえません。
建物取壊しの場合に立退料を請求できないとする規定が問題となったケース
建物の老朽化のための立ち退きにおいて、立退料を請求できなくする定めがしばしば見られます。
確かに、崩壊寸前の建物など、そもそも賃貸借契約の履行が不可能な状態になっているのであれば、契約は当然終了となり、立退料の問題は生じないでしょう(もっとも、住めなくしたことに賃貸人の帰責性があれば、別途、損害賠償請求の話になります。)。
しかし、通常、立退料が問題となるのは、まだまだ住めるのに、賃貸人が建て替えを実行しようとする事案です。
建物の老朽化は、賃貸人の建物使用の必要性を肯定する要素となりますが、他方で、賃借人の建物使用の必要性も保護されなければなりません。通常、建物の老朽化のみで、賃借人の建物使用の必要性を明らかに上回ると認定することは困難であることから、多くの場合、立退料は必要になる可能性は高いです。
立退料を放棄させるような契約書の記載を肯定したケース
契約書の記載内容の効力を判断するにあたって、実際に裁判所がどのように判断しているのかを知ることも非常に参考になります。まずは、効力を肯定した2つの事案を見ていきましょう。
期限付合意解約
従来から存続している賃貸借契約について期限を設定しその期限が到来すると解約になるという、期限付き合意解約は、原則として有効と解釈されています(最高裁判所判決昭和31年10月9日民集10巻10号1252頁)。
誤解されやすいのが、「期限」とは、何年何月何日の経過という意味を指しているのであって、「条件」ではないということです。賃貸人側の「条件」によって明渡し時期が左右される特約は無効と判断されることが通常ですから、「期限」か「条件」かの区別は極めて重要となります。
よくある「条件」の具体例として、「海外出張していた賃貸人が戻ってきた場合」と契約書等に記載することがあります。賃貸人が戻ってくるのは、1年後かもしれませんし、10年後かもしれませんので、賃借人の地位は、賃貸人の都合によって大きく左右されることになります。
このように、賃借人において、明確に明渡し日を確定できないような場合は「条件」と扱われることになります。
社宅を明け渡す旨の特約
雇用契約が終了となり、会社員としての資格を失ったときは直ちに立ち退くべき特約が争われた事例において、判例は、支払っている社宅料が低額であったことを理由に「社宅使用の対価ではなく、賃貸借関係ではない」として、特約の効力を肯定しました(最高裁判例昭和29年11月16日民集8巻11号2047頁)。
反対に、家賃として相応の社宅料を支払っていた事案であれば、賃貸借であるとして、社宅を明け渡す旨の特約を無効とした裁判例もあります。
結局、判例の考え方としては、社宅使用料が、「家賃」とみることができるかによって賃貸借契約の有無を判断しているようです。
立退料を放棄させるような契約書の記載を否定したケース
他方、実質的には立退料を放棄させるような規定を無効とした裁判例は多くあります。それぞれ、見ていきましょう。
賃貸人の要求があるときはいつでも即時家屋を明け渡す旨の特約
賃貸人の要求があるときはいつでも即時家屋を明け渡す旨の特約が入った賃貸借契約書を交わされていたケースがあります。
裁判所は、このような特約は賃借人の権利の安定を保障する法律に反するとして、その効力を無効としました(神戸地方裁判所昭和31年10月3日判決下民集7巻10号2806頁)。
更新拒絶の制限の規定に反する特約
更新拒絶等を無条件に認める特約の効力が問題となったケースがあります。裁判所は特約を無効と判断しています(大阪高等裁判所判決昭和31年5月21日判例時報84号9頁)。
また、期間満了と同時に借家契約が当然終了する旨の特約があったケースについて、裁判所は一時使用の賃貸借契約と認められない限り、無効であるとしています(大阪地方裁判所昭和40年1月21日判タ172号149頁)。
違約金の支払いを求める特約
期間満了後に建物を明け渡さないときは違約金を支払う旨の特約があったケースについて、裁判所は、正当事由の判断をさせずに明渡しを強制しかねないものであるとして借地借家法30条によって無効と判断しています(佐賀地方裁判所判決昭和28年3月7日下民集4巻3号348頁)。
立退料に関する合意契約書の記載内容
弁護士を介さずに、当事者間で立ち退き交渉を行い、合意書を締結させる例も珍しくありません。しかしながら、合意書の内容に納得できず、せっかく締結した合意書の内容が履行されないこともあるので、賃貸人と賃借人の双方が納得できる合意書を作成する必要があります。
合意書を作成するにあたり、気を付けるべき点をそれぞれ見ていきましょう。
合意契約書のひな型はあるのか?
ひな形はインターネットを検索すればいくつか見つかるでしょう。いかなる立退き案件にも共通する条項はひな形のまま使用することができます。
しかし、多くのケースでは、当該ケースに特有のポイントがありますので、それを盛り込むことが重要となります。
立退料の支払条件の定め方
賃貸人としては、高額な立退料を支払ったにもかかわらず、賃借人が立ち退きに応じない事態は避けたいところです。また、賃借人としても、せっかく立ち退きに応じたにもかかわらず、約束した立退料が支払われない事態を避けたいと考えるのが通常です。
明渡し前に立退料の一部を支払い、明渡し完了後に残金を支払うという条件とすることが通常です。
明渡期限の定め方
立退料の支払いを受けてから、すぐに引っ越し先の物件を探すとしても、新規の賃貸借契約を締結するまでに1か月は最低かかります。
少なくとも2か月程度の猶予期間を設けることが一般的ですが、さらに長期の明渡し期限を定めることがあります。
その他契約書に盛り込むべき内容
明渡しにあたっては、原状回復、残置物処理の問題は避けて通れません。
原状回復などの費用をだれが負担するのかについても定めておく必要があります。
まとめ
契約書に記載されている内容が全てではなく、借地借家法が保護している賃借人の権利を失わせるような条件は、借地借家法に基づいて無効にすることができます。
このように、賃借人の最低限の権利が強く保障されていることを前提としつつ、賃貸人・賃借人がそれぞれ正しい法律知識を持って交渉に臨むことが重要です。
とはいえ、それでも世の中には様々な契約書が生まれており、非常に判断が難しくなる事案も存在しています。そのような事案では、専門家弁護士のアドバイスの下、適切に交渉を進めていくことが、円満な立退料交渉の解決の近道になるでしょう。