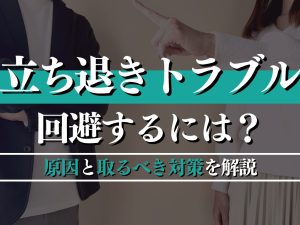立退料とは?役割・算定方法と相場・消費税法上の取り扱いと具体的なケースを弁護士が解説
最終更新日: 2023年11月29日
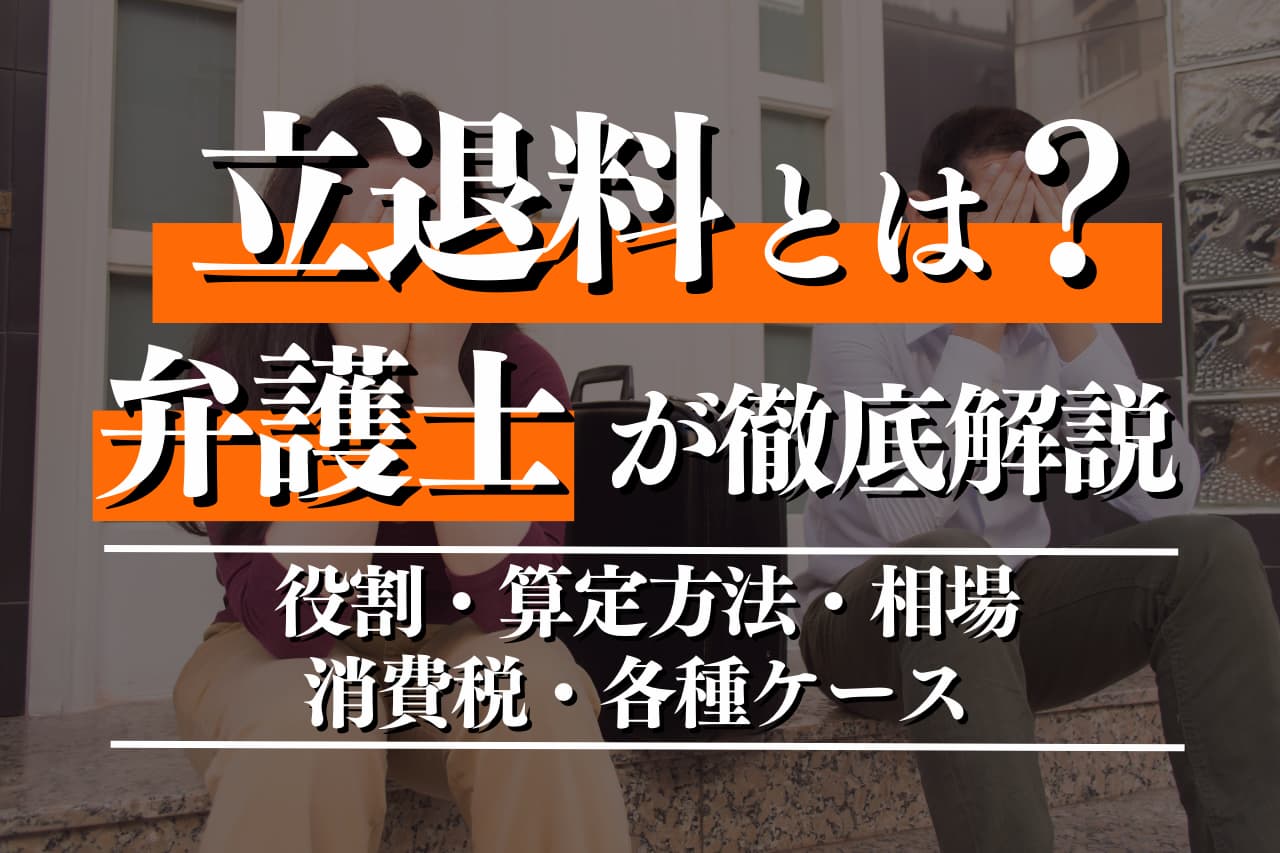
- なぜ自分の物を返してもらうのに、立退料を支払わないといけないのか
- 出て行ってほしいと言われても、出ていくための費用もない。補償をしてほしい
- どういう場合にいくらぐらいの立退料が発生するのかを知りたい
近年では、老朽化した建物が急増し、これに伴って立ち退き交渉の事案も非常に増えています。中には、交渉に行き詰まり、賃貸人・賃借人を問わず、解決できない問題に困っている方も多いのではないでしょうか。
この増加する立ち退き交渉について、解決の鍵を握るのが、まさに「立退料」です。
そこで今回は、多くの立ち退き交渉を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、立退料とは何か?という根本的な問題について、深く掘り下げながら解説していきたいと思います。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 十分な正当事由がなければ立退料は発生する
- 立退料は状況によって支払い不要・請求できない場合もある
- 立退料の交渉は対応実績が豊富な弁護士に相談することが大切
立退料とは?定義と法的根拠
立退料とは、正当事由が十分にない状態で賃貸借契約の期間を賃貸人が更新をしない場合に、賃借人に対して支払う補償金です。
借地借家法第28条では、賃貸借契約は契約更新することが原則とされており、正当な事由がある場合にのみ更新を拒絶できるとされています。
実は、元々、立退料という言葉は、法律上存在していませんでした。
明渡しの裁判では、賃貸人と賃借人が、それぞれの正当事由を戦わせるものの、最終的には、裁判所が調整要素として、賃貸人が賃借人に支払う補償金を求めるようになり、この金銭によって多くの立ち退き紛争を解決してきました。
立退料は、そのような裁判例が積み重なり、生まれた概念です。
そのため、立退料は事案ごとに内容は様々です。引っ越し代の補償、賃借権を譲渡する対価、営業補償など、様々な名目に変わる金銭として、賃貸人から賃借人に対して支払いがなされてきました。
現在、立退料は「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として・・・賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」(借地借家法28条)によって法的根拠を得ています。
立退料の役割【賃貸人・賃借人別】
ここまでは、立退料の沿革や、内容について見ていきました。次は、立退料の役割について賃貸人・賃借人の両面から見ていきましょう。
賃貸人における役割
賃貸人における立退料の役割として以下の4つを解説します。
- 正当事由
- 家賃差額の補償
- 営業補償や休業補償
- 慰謝料
正当事由
立ち退き請求に必要なのは、賃貸人の建物利用の必要性を基礎づける正当事由であって、立退料ではありません。賃貸人の建物利用の必要性さえ認められれば、本来、立退料は必要ではないのです。
しかしながら、賃貸人の建物利用の必要性が、賃借人のそれを明らかに上回ることが求められます。どちらの必要性も甲乙つけ難いということでは、賃貸人の正当事由が肯定されることはないため、正当事由を補完する要素として立退料が用いられるのです。
そして、正当事由を肯定するための立退料として、賃貸人がいくら提示すべきかが問題となります。
立退料は、賃借人を一方的な都合で退去させても不当ではないと言えるだけの補償が必要となります。
家賃差額の補償
急に立ち退きを求められても、現在借りている物件と同一の立地、間取り、広さの物件を見つけるのは、極めて困難です。
そのため、現在借りている物件と同じような物件で契約しようとすると、どうしても家賃の部分で妥協しなければならなかったり、全く別のエリアに引っ越しせざるをえなかったりするのです。
賃貸人の方は、自身の都合で、賃借人に対して退去をお願いする立場のため、立ち退きによってマイナス影響が出るようでは、誰も立ち退きに協力しないでしょう。このような観点から、家賃差額の補償が求められています。
営業補償や休業補償
店舗の立ち退きを求める場合、賃借人が新店舗に移転し、開店できるようになるまで、お店を休業しなければなりません。
お店を休業する以上、賃借人は収入を得る手段が途絶えるわけですが、店舗の賃料はもちろん、取引先への支払い、借入金の返済、税金の支払いをしていく必要があります。もちろん、賃借人自身の生活費もありますし、従業員への給料の支払いをする必要もあるでしょう。
このように店舗の立ち退きにおいて賃借人が多大な損失を被ることから、立退料は、賃借人が被るであろう、営業補償や休業補償として支払いが必要となる場合があります。
慰謝料
立ち退きは、賃借人に対して、引越しをお願いするものです。立ち退きがなければ負担する必要がなかった損失、実費については、賃貸人から支払われる立退料で回復できるとしても、引越しには相当な労力と時間を費やさなければなりません。
新しい物件を探すには、休日を返上して、不動産屋をいくつも回る必要がありますし、引越し作業の前提となる荷造りも相応の労力を要します。
結局、賃借人が負担した実費ベースでの補償では、立ち退きにかけた労力と時間に見合わないので、慰謝料としての立退料も必要でしょう。
賃借人における役割
よく誤解されがちですが、立退料とは、賃借人に認められた権利ではありません。賃貸人から具体的な申し出があってはじめて支払われるものであり、法律上、賃借人に「立退料請求権」というものが発生する根拠はどこにもありません。
そのため、賃借人が賃貸人に対して、立退料を支払うよう裁判所に提訴したとしても、裁判所は賃借人の賃貸人に対する立退料請求を棄却する(賃借人の敗訴)しかありません。
立退料は賃借人の請求権ではないので、賃貸人が立ち退きを断念してしまい、立退料の提示がなくなってしまうと、それ以上賃借人の力では、支払いを強制することができないのです。法律上はあくまで「賃貸人からの提案」の一つにすぎないものであり、請求する権利を有しているわけではないという点を心得ておく必要があるでしょう。
立退料の算定方法と相場
立退料の算定は、まず、賃貸人と賃借人の双方の正当事由の比較によって大枠が定まります。
極論として、賃貸人の請求に正当事由が認められるのであれば、立退料は不要です。しかし、明確に賃貸人の正当事由の方が上回っているという事案は、なかなか見られないため、多くの事案では立退料による正当事由の補強が不可欠です。
引越し費用、新規契約にかかる諸経費はほとんどの事案で認められています。算定が難しいのは、当面の生活保障として支払われる家賃差額や、営業補償の金額です。
もちろん、慰謝料としての部分もどこまで認められるのか問題となることが多いです。
営業用賃貸物件・店舗賃貸物件となると、事案によって認められる金額は様々であり、一般化は困難でしょう。
他方、居住用に関しては立ち退きに要する費用や損失は大きく変わらないため、単身用の立ち退き事案では100~150万円の立退料が多いと思われます。
なお、立退料の算定について、以下で詳しく説明していますので、気になる方はご参照ください。
立退料が支払い不要・請求できないケース
これまで立退料が支払われることを前提に、立退料について説明をしてきましたが、どのような立ち退き事案であっても、立退料が支払われるわけではありません。
以下では、立退料が支払われない事案について紹介していきます。
- 定期建物賃貸借契約
- 債務不履行
- 解約合意書へのサイン
定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約とは、更新が予定されていない建物の賃貸借契約のことで、借地借家法の更新拒絶に関する定めの適用はなく、契約した期間の経過により、当然に終了となります。
なお、定期建物賃貸借契約というためには、賃貸借契約締結時に厳格な要件が課されているので(借地借家法38条)、前述した借地借家法30条には反しません。
更新拒絶に関する定めの適用がないということは、契約終了にあたり、正当事由が不要ということになります。立退料が必要となるのは、賃貸人の正当事由を補完するためですから、そもそも論として正当事由が不要ということになれば、立退料を支払う根拠がなくなります。
したがって、定期建物賃貸借契約における賃借人は、立退料の支払いがなければ退去に応じないと主張することはできません。
ご自身の契約が定期建物賃貸借契約かどうかは、事前に確認しておく必要があります。
債務不履行
不法占拠者を退去させる場合、立退料は不要です。
不法占拠者の具体例としては、何の使用権限もなく建物に居座っているような場合が典型ですが、元々は賃貸借契約に基づいて建物に住んでいたものの、途中から賃料を滞納するようになって、賃貸借契約を解除された賃借人もこれに該当します。
このようなケースにおいて、賃借人(あるいは建物利用者)は、賃貸人の一方的な明渡請求に応じなければならず、立退料の支払いはありません。
もっとも、不法占拠者は、往々にして、開き直って居座り続けるケースが散見されます。
この場合、当該不法占拠者に対して、訴訟提起・明渡しの強制執行をすることで無理矢理にでも退去を実現させることができますが、弁護士費用・裁判費用に相応のコストを要するので、注意が必要です。
事実上、引っ越し代程度の立退料を支払った方が、スムーズに退去を実現できることも多いので、選択肢の一つとして押さえておくとよいでしょう。
解約合意書へのサイン
賃貸借契約満了のタイミングで、賃貸人と賃借人の間で、解約合意書を作成した場合です。
これは実際にもよく起こる事案であり、突然、管理会社から、次回の契約更新はないと言われ、立退料の提示もないまま、解約合意書にサインしてしまうケースがあります。
この場合に借地借家法30条の規定を適用して、無効にすることができるのか、問題となります。しかし、借地借家法31条は、「不利」なことが求められるところ、解約合意書にサインをしたという事案では「不利」とまでは認められないと言われる可能性が高いです。
したがって、解約合意書にサインをした場合、たとえ立退料の提示がなかったとしても、後からこれを覆すことは難しいでしょう。
立退料を請求しない特約は無効
立ち退きが問題となった事案において、よくあるのが、賃貸借契約書に「立退料を請求しない」旨の記載がある場合です。このような場合、賃借人は、賃貸人から一切の立退料を支払ってもらえないのでしょうか。
先ほども少し触れましたが、借地借家法には、契約の特約のうち賃借人に不利なものを無効とする規定があります(借地借家法30条)。この借地借家法30条の典型的な適用例としては、契約更新のとき、賃貸人において正当事由を不要とする特約を置いている場合などが考えられます。これは、借地借家法の更新拒絶規制の趣旨を没却することになるので、明らかに無効というべきでしょう。
したがって、正当事由を具備すべきという借地借家法の記載を無にするような特約に合意してしまったとしても、原則として無効になりますから、この場合、立退料の支払いなく、賃借人が一方的に建物を明け渡さなければならない結論にはなりません。
契約書に立退料を請求しない特約があったとしても、賃借人としては、毅然として、立退料の支払交渉をすべきでしょう。
立退料の消費税法上の取り扱い
立退料が一時所得として扱われることから、立退料に消費税が含まれるのかどうか問題になることがあります。もし、立退料に消費税が含まれるとすれば、10%もの消費税を含むことになるため(2023年3月時点)、切実な問題です。
ただ、立退料に消費税が含まれるかどうかは、その支払われた経緯や、内容に踏み込まないと判断ができないため、一概に消費税が課税されるとは言い切れません。損害賠償金として扱われれば、消費税として課税される可能性は低くなり、他方で、高く賃借権を売却した対価との側面が強く出てしまうと、資産の売買と同視されて消費税が課税される可能性が高まります。
立退料に消費税が含まれるかどうかは、かなりあいまいな部分を残します。意外にも後から消費税として課税されるリスクも残ることになるため、気になる方は税理士にご相談することをお勧めします。
立退料の交渉・調停・裁判をケース別に紹介
賃貸借の契約期間が満了するまでに、賃貸人と賃借人との間で立退料の金額交渉がまとまった場合は、問題はありません。しかし、現実は、必ずしもそのように上手く交渉がまとまる事案ばかりではなく、交渉がまとまらないまま、賃貸借の契約期間が終了してしまうという事態が起こります。
このように賃貸借契約の契約期間が満了してしまったのに、立退料の交渉がまとまっていない場合、賃貸人・賃借人は、それぞれどのように動くべきなのでしょうか。
立退料を受け取らずに契約期間満了になった場合
元々の賃貸借契約は、法定更新されて期限の定めのない賃貸借契約として残り続けます。この場合、従前のとおり定めた賃料を支払い続けることで、賃借人は、建物に居住し続けることができます。
したがって、賃貸借契約の契約期間が満了したとしても、強制退去になるわけではありません。
他方、賃貸人としては、期間満了後の賃貸借契約が「期限の定めのない賃貸借契約」に変わったことから、賃借人に対して、6か月後に契約が終了する旨の通知をすることで、当該賃貸借契約を終了させることができます。もちろん、この場合でも正当事由が必要となるため、このタイミングで立退料の提示をすることになります。
賃貸人から契約終了通知をして6か月が経過したにもかかわらず、賃借人が退去に応じない場合には、明渡しの訴訟を提起するかどうかを賃貸人が決断しなければなりません。
賃貸人が明渡しの訴訟を提起した場合
もし賃貸人が明渡しの訴訟を提起して、その請求に正当事由が認められた場合、賃借人は、強制退去に応じなければならないのか、不安があるものと思います。
しかし、明渡しに正当事由が問題となる事案において、担当裁判官が、判決に進む前に、双方の目安となる立退料を事前に示してくれることが多いと思われます。裁判官から示された立退料の金額に問題がなければ、立退料の支払いを受けてから、明渡しに応じる条件で取り決めをすれば安全です。
また、判決に進んだとしても、通常は、立退料の支払いと引き換えに建物を引き渡すという、引換給付判決が出されます。そのため、賃借人が、立退料の支払いを受けることなく、一方的に退去強制させられることはありません。
老朽化したマンションを取り壊す場合
老朽化マンションを取り壊すためには、区分所有法と建替え円滑化法という法律の規定に基づく、マンションの建て替えという手続きをとることができます。
賃借人は、新マンションへの賃借権設定を希望することができるものの、価値の高い新築マンションに変わるため、賃料が大きくアップするのが通常です。
そのため、賃借人は、マンション建て替えを機に引っ越しをするのが通常で、新たな賃借権を設定するケースはまれです。
新たな賃借権設定を希望しない賃借人は、補償金の支払いを受けて転出することが可能ですので、建て替え側との間において、補償金の支払いを受け取る代わりに任意の立ち退きに応じる合意書を締結することになります。
なお、建替え円滑化法に則った建替え手続きであっても、マンションの取壊しに消極的な賃借人との契約を終了させるためには、正当事由が必要となることは、通常の立ち退き事案と変わりません。
転借人も交渉する場合
「転貸借」と聞くと、「転売」「又貸し」というワードを連想し、少しいけないことをしているというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、よくある「サブリース方式」も転貸借を用いており、世間に「転借人」と呼ばれる方は、たくさんいます。このように、転借人も、賃貸人の同意を得て、当該物件を使用しているのですから、一方的に退去を求めるのであれば、その地位を守る必要があることに変わりありません。
ただし、転借人が立退料の交渉をする相手は、賃貸人ではなく、「転貸人」になります。転借人は、賃貸人と何の契約関係もないからです。
再開発で交渉する場合
いわゆる再開発エリアについては、複数のデベロッパーが再開発組合を結成し、都道府県知事の認可を得た上で、都市再開発法に基づく建替えを実行することができます。
老朽化マンションの建替えのところで述べたことと規制内容は類似しており、賃借人は、再開発エリアの賃借権を得るか、補償金の支払いを受けて退去するかを選択できます。
もっとも、再開発による既存物件の価値上昇は著しいものがあるため、再開発の「権利変換」により衛生の向上・居住条件の改善という一般的基準に適合した新たな財産を与えることができない「過小床」(要するに、生活に最低限必要なワンルームにもならない場所しか与えられない状態)になってしまうことがほとんどです。
したがって、賃借人は、ほとんどの事案において、「権利変換」を行わず、補償金の支払いを受けて退去することになるでしょう。
まとめ
今回は、立退料に関する法律問題について、様々なケースを交えながら、多角的な視点で立退料の意義を解説しました。
立退料は、主張する立場によってその中身が様々であることをお分かりいただけたと思います。立退料交渉をするにあたり、賃貸人の方は、なぜ賃借人が退去にあたり立退料を必要とするのかを考える必要があり、他方で賃借人の方は、賃貸人にはそもそも立退料を支払う法的義務がないという前提を理解する必要があります。
いずれの立場であっても、相手の立場を理解しないと立退料交渉の解決は決裂してしまいます。交渉が難しいと感じた場合には、一度、専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。